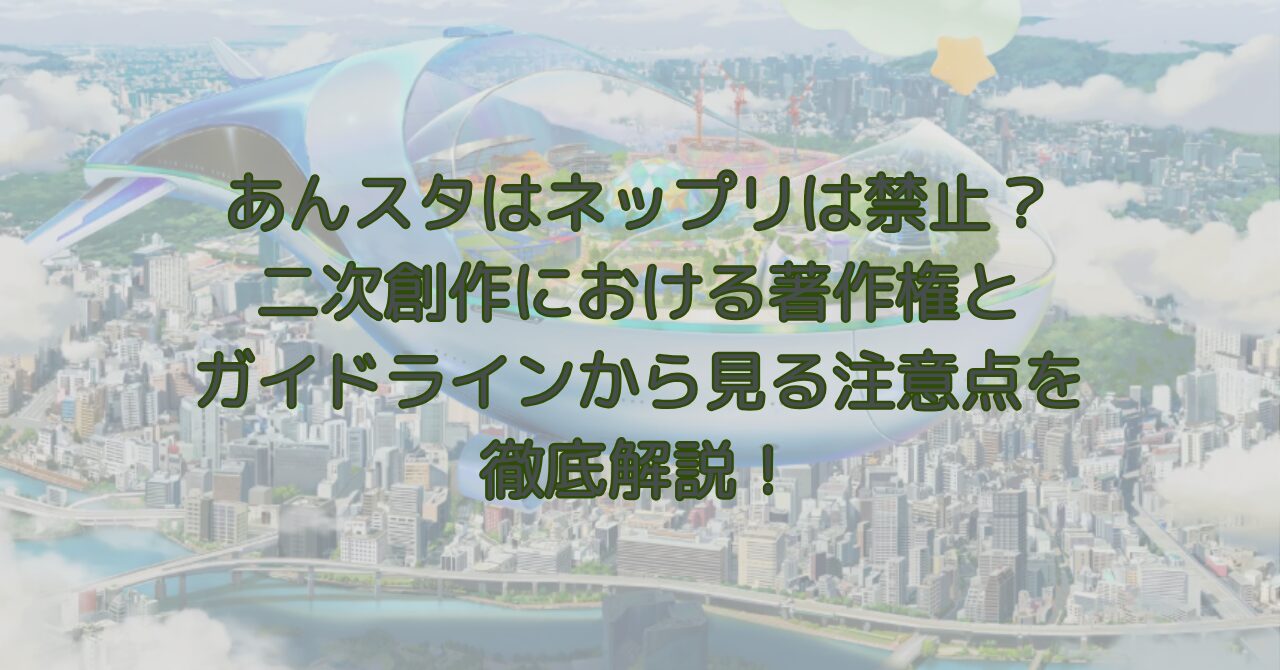「あんスタはネップリって禁止なの?」
「過去に炎上したって聞いたけど、何が問題だったの?」
そんな疑問を持って検索している方に向けて、この記事では「あんスタ(あんさんぶるスターズ!!)」におけるネップリ配布の禁止ルールや過去の炎上事例、そして安全に二次創作を楽しむためのルールを詳しく解説します。
また、自作グッズの扱いや同人イベントでの注意点など、クリエイターやファンとして知っておきたい情報まとめました。
自分の作品を大切にしながら、あんスタの世界をみんなで安心して楽しむためにぜひ最後まで読んでみてください。
あんスタはネップリ禁止!理由と過去事例を紹介!
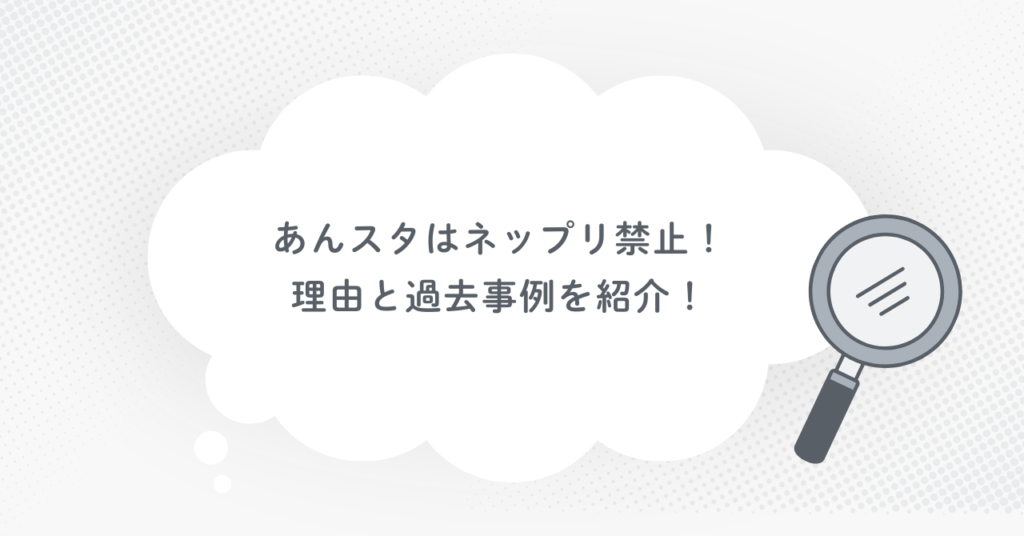
あんスタの二次創作を楽しむファンにとって、自由にイラストを描いたり、キャラクターを題材にした作品を公開することは魅力のひとつです。
あんスタには公式が二次創作ガイドラインを定めていて、そこでは、創作活動の自由とファン活動の楽しみを尊重しつつも、守るべきルールが明確に示されています。
その中でも特に明確に禁止されているのが、「ネップリ」です。
ここでは、なぜネップリが禁止されているのかや、実際に起きた問題事例について詳しく紹介します。
ネップリが禁止の理由。禁止行為について

まず、ネップリとは「ネットプリント」の略称で、コンビニのコピー機を利用してインターネット上にアップロードされた画像や文書を印刷できるサービスを指します。
利用者はプリント番号を入力するだけで、イラストや写真を簡単に印刷できるため、同人やファン活動においても広く使われています。
しかし、この「誰でも印刷できる状態」という仕組みが、あんスタのガイドライン上で大きな問題となります。
公式が求める「私的利用の範囲」とは、基本的に自分や限られた友人など、閉じた環境で楽しむことを指します。
一方、ネップリはプリント番号さえ知っていれば不特定多数がアクセスでき、作品を入手できてしまうため、著作権法上の「公衆送信」に該当する可能性があります。
これは、営利・非営利に関係なく公式の権利を侵害しやすい行為とされ、ガイドラインでも禁止行為に明記されています。
たとえ自作イラストであっても、あんスタのキャラクターを描いたものをネップリで配布する行為は、「公式が許可していない方法で作品を不特定多数に配布する」ことになり、ルール違反となります。
特にTwitterなどSNSでプリント番号を公開すれば、事実上の大量配布となるため、炎上や通報の対象になりやすいです。
このため、ガイドラインでは「ネップリでの配布は禁止」と明確に線引きされています。
無料配布であっても例外ではなく、「お金を取らなければ大丈夫」という認識は通用しません。
公式は、二次創作を楽しむファンのために一定の自由を認めていますが、その範囲を超える行為には厳格に対応する姿勢を取っています。
ネップリ配布がTwitterで批判・炎上した事例
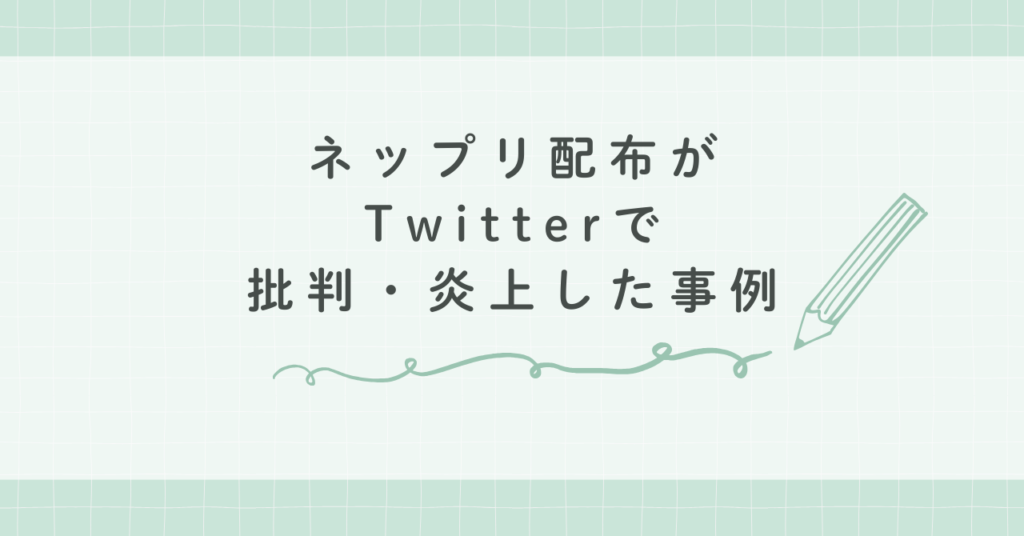
過去にはTwitter上でルールを知らず、あるいは軽視して行ったことが原因で批判や炎上に発展したケースがありました。
代表的な事例としては、ファンアートやキャラクターイラストをネップリ登録し、そのプリント番号をTwitterで公開してしまったケースです。
投稿者としては「無料配布だから問題ないだろう」「イベントに来られない人にも届けたい」という善意で行ったことだったとしても、SNS上で公開されたプリント番号は誰でも利用可能であり、結果的に不特定多数に作品が配布される形になります。
これはガイドラインで禁止されている「公衆送信」に該当する可能性が高く、著作権侵害のリスクがあります。
炎上時の反応としては、まず他のファンやガイドラインを熟知しているユーザーから注意喚起のリプライや引用RTが行われ、その拡散によって投稿者が一気に批判の対象となりました。
中には「ルールを守らないファンは公式や他のファンに迷惑をかける」という厳しい意見も多く、投稿を削除して謝罪する事態にまで発展しています。
この種の炎上は、ルールを知らない新規ファンや、他ジャンルではネップリ配布が黙認されているケースを参考にしてしまった人が起こすことが多いです。
しかし、あんスタではネップリが過去の炎上やトラブルの温床になってきた経緯があり、公式は繰り返しガイドライン遵守を呼びかけています。
特にSNS時代では、ちょっとした配布方法の違反でも、画像やプリント番号がスクリーンショットとして残り、長期間拡散される可能性があります。
そのため、「善意だから大丈夫」という認識は非常に危険です。
あんスタの二次創作を安全に楽しむためには、必ず公式の二次創作ガイドラインを確認し、ネップリやそれに類する方法での配布は行わないことが鉄則といえます。
あんスタ二次創作のガイドラインを解説!ネップリ以外の禁止事項は?
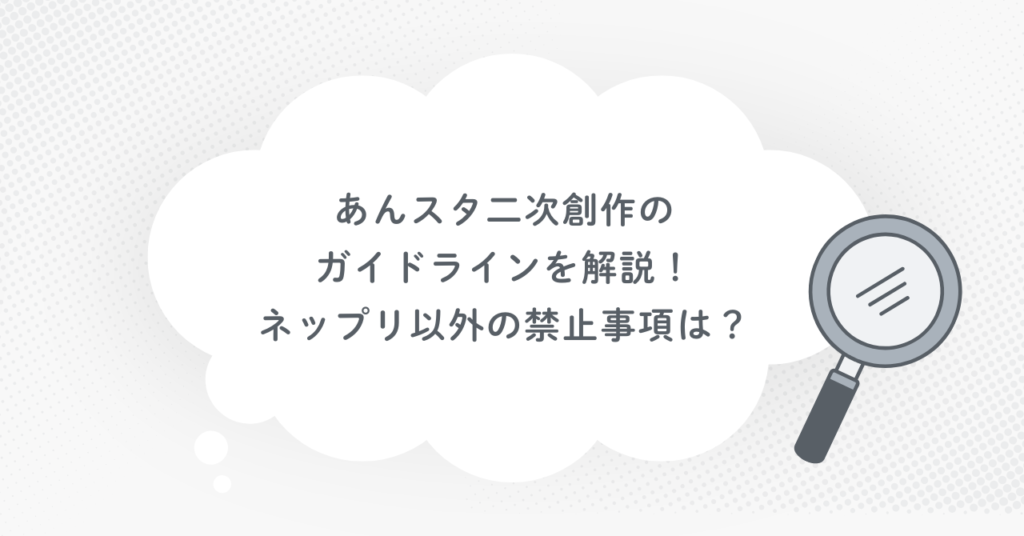
二次創作活動は、ファンが作品への愛情を表現する大切な手段のひとつです。
あんスタのファンの中にも、イラストや漫画、グッズを通じてキャラクターへの想いを形にしている人は多いでしょう。
ですが、その一方で「これは大丈夫?」「ここまでやったらアウト?」と判断に迷う場面も少なくありません。
とくにネップリのように明確に禁止されているケースだけでなく、グッズ販売や作品公開の方法次第でガイドライン違反になってしまう可能性もあるため注意が必要です。
ここでは、著作権と二次創作ガイドラインの関係を踏まえつつ、ネップリ以外の禁止事項や、同人グッズ販売で気をつけるルールを解説していきます。
あんスタにおける著作権と二次創作ガイドライン
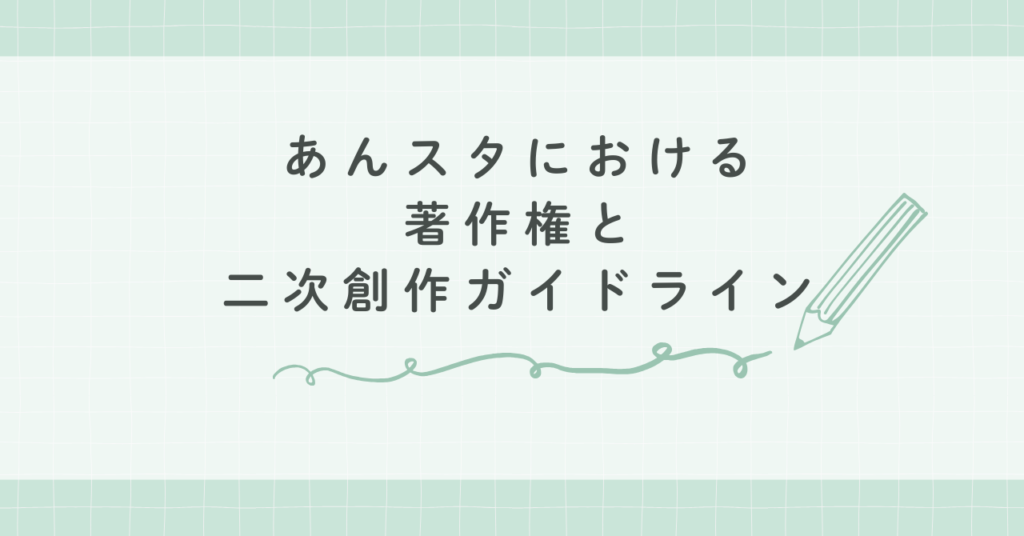
あんスタの二次創作を楽しむにあたって、まず押さえておきたいのが著作権と公式ガイドラインの存在です。
あんスタに登場するキャラクターやイラスト、ストーリー、音楽などは、すべて著作権で保護されています。
著作権とは、作品を創作した人や権利者が、その作品の利用や複製、頒布を独占的に管理できる権利です。
つまり、ファンであっても公式の許可なく作品をコピーしたり、商用利用したりすることは法律で制限されていて、ファンが自由に創作を楽しめる範囲は決められています。
この範囲を理解せずに作品を公開したり、グッズを頒布したりすると、意図せずトラブルに巻き込まれることがあります。
特に、SNSでの画像投稿や、夢絵、グッズ販売など、インターネットや同人イベントを通じて行う活動では注意が必要です。
あんスタの二次創作は、「ファン個人の趣味の範囲で、非営利目的」であれば、公式から黙認・容認されています。
このガイドラインは、ファン活動を禁止するためではなく、「みんなが安心してあんスタを応援し、楽しめるように」という目的で定められています。
細かいルールはたくさんありますが、最も重要なルールは次の3つといえるでしょう。
- 公式や関係者に迷惑をかけない!
- お金儲けをしない!(非営利の原則)
- 公式の素材をそのまま使わない!
まず、公式や関係者に迷惑をかけないためには、公式タグの使用を避けることが重要です。
腐向け(BL)、夢向け、R-18など、人を選ぶ作品を投稿する際に、「#あんスタ」 のような公式タグを使うのは控えましょう。
また、原作者の日日日先生や声優、イラストレーターのSNSに二次創作イラストを送ったり、自分の解釈をリプライで伝えたりすることも避けるべきです。
お金儲けを目的とした活動も禁止されています。
二次創作で作った同人誌やグッズで生活できるほどの利益を得ることは認められません。
趣味の活動にかかった費用、たとえば印刷代などを回収する程度に留めることが基本です。
さらに、公式の素材をそのまま使用することも避けなければなりません。
ゲーム内のイラスト、ロゴ、背景、音楽などをコピーしたり、トレース(なぞり描き)して自分の作品に使うことは著作権侵害にあたり、固く禁止されています。
必ず自分の手で描き、自分の創作物として表現することが求められます。
公式はファン活動の自由を尊重していますが、著作権侵害となる行為には厳格に対応する姿勢を示しており、過去には不適切な画像加工や無断頒布に対して法的措置を取った事例もあります。
二次創作を楽しむためには、これらのことを意識・理解することが必要です。
二次創作のグッズや作品、何がOKで何がNG?
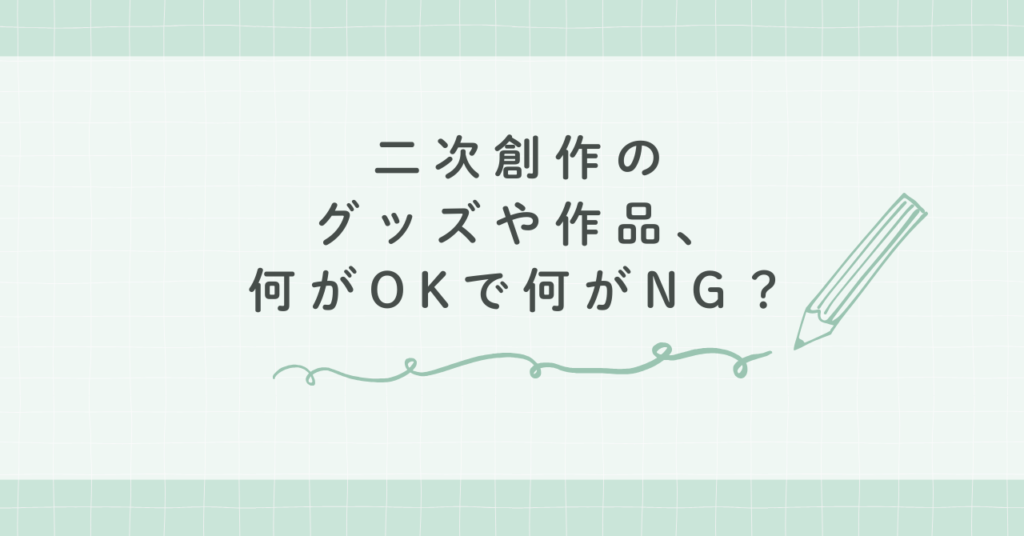
あんスタの二次創作活動には、イラストや漫画、グッズ制作などさまざまな形があります。
しかし、自由に創作できる一方で「どこまでが許されるのか」「これはNGにならないのか」と悩む場面も少なくありません。
ここからは、二次創作作品の種類ごとにOKとNGの境界線を紹介していきます。
二次創作の漫画は作っていい?

あんスタの二次創作漫画については、公式が定めるガイドラインに従うことで、基本的には作成・頒布が認められています。
自作の漫画やイラスト、小説、批評などの二次的著作物は、行き過ぎた利益追求をしていない場合には非営利目的として扱われます。
同人誌の場合、販売時の制限や売上額の上限も基本的に設けられていないため、印刷方式や頒布形態に大きな制限はありません。
ただし、同人誌に含まれる付属物や印刷物がグッズとしての性質を強く持つ場合は、営利目的として判断されNGとなることがあるため注意が必要です。
また、過度に攻撃的、暴力的、または公序良俗に反する表現は、公式が判断して頒布停止や削除を求める可能性があります。
つまり、漫画や小説など紙媒体の二次創作物については、あくまで創作活動の自由を尊重する一方で、公式ルールや社会的マナーに沿った内容であることが前提となります。
安全に楽しむためには、売上の管理や内容の取扱いをガイドラインに沿って行うことが必須です。
自作トレカは作っていい?
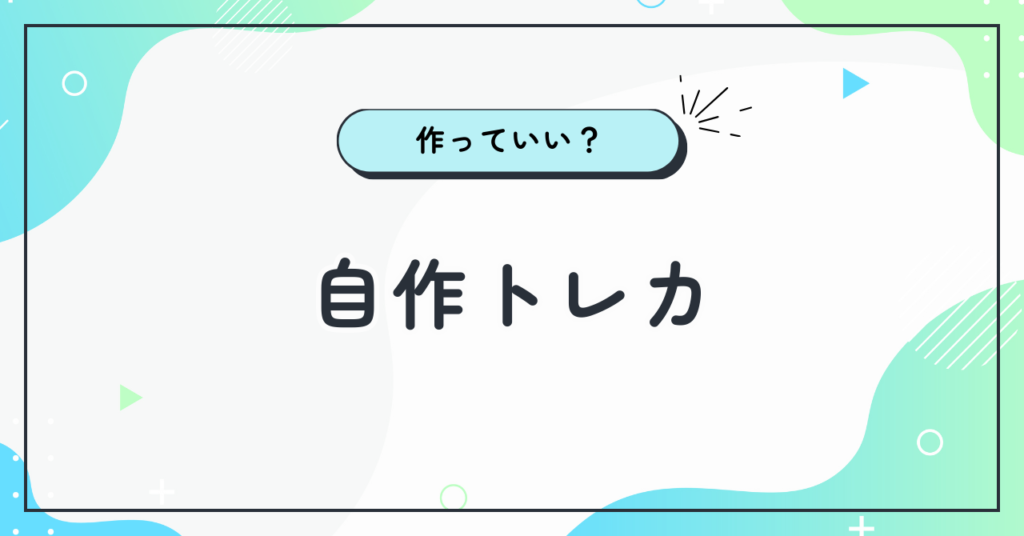
自作トレカはどこまで許されるのでしょうか?
結論から言うと、自分だけで楽しむ範囲であれば基本的に問題はないとされています。
例えば、家でコレクションとして保管したり、身近な友人に「こんなの作ってみたんだよ」と見せる程度であれば、非営利かつ私的利用の範囲内として黙認されるケースが多いです。
ただし注意が必要なのは、配布・交換・販売といった行為です。
自作トレカをフリマアプリやオークションで出品するのはもちろん、公式グッズのように交換会などで扱うことも、著作権や商標権の侵害にあたる可能性が非常に高く、避けるべきです。
また、SNSやネット上に画像を公開する行為もグレーゾーンです。
非営利であっても、ダウンロード可能な状態で配布してしまうと「実質的に配布」と見なされ、トラブルに発展する可能性があります。
公式もガイドラインで「無断でグッズ化・配布・販売はNG」と明言しています。
さらに、公式イラストをそのままスキャンして使ったり、公式品と誤解されるようなデザインで公開するのは完全にアウトです。
つまり、あんスタの自作トレカは
- 自分だけで楽しむ範囲 → OK
- 他人に配布・販売・大規模公開 → NG
この線引きを守ることが大切です。
推しへの愛を形にするのは楽しいですが、必ず「私的利用の範囲」にとどめて楽しみましょう。
スチルは印刷してもいい?
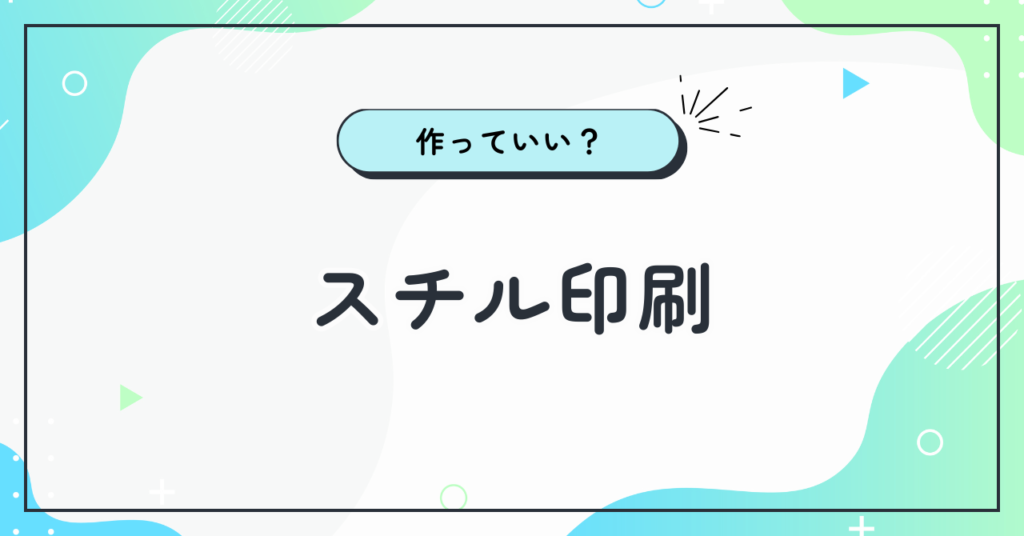
スチルの印刷は許されるのでしょうか?
結論から言うと、「自分だけで楽しむ私的利用の範囲」ならOKとされています。
例えば、以下のようなケースです。
- 自宅でプリントして部屋に飾る
- 手帳や日記に貼って個人的に楽しむ
- スマホの待受や壁紙として利用する(印刷ではないが「複製」と同じ扱い)
著作権法でも「家庭内などごく限られた範囲で楽しむ私的使用」の場合に限り、複製が認められています。
つまり、自分や家族だけで楽しむ閉じた範囲であれば大きな問題はないのです。
一方で、「私的利用」を一歩でも超えた行為はすべて著作権侵害にあたります。
特に次のケースは注意してください。
- SNSへの投稿
印刷したスチルを撮影してTwitterやInstagramにアップするのは「公衆送信権」の侵害になります。
たとえ自作感覚であっても完全にアウトです。 - 他人への配布・交換
友達にあげたり、イベントで交換に出すのもNG。
無償でも「複製物を配布する行為」は私的利用を超えてしまいます。 - 販売やオークション出品
印刷したスチルをラミネートして「自作グッズ」として販売するのは、悪質な著作権侵害にあたり訴訟リスクすら伴います。
あんスタを運営するHappy Elementsも「コンテンツ利用に関するガイドライン」で、公式イラストやスチル画像を無断で転載・配布・販売する行為を禁止しています。
つまり公式としては「ゲームの中や公式グッズで楽しんでほしい」というスタンスです。
推しのスチルを手元で楽しむ気持ちは理解されやすいですが、ルールを超えると著作権侵害につながります。
あくまで「自分だけで楽しむ範囲」にとどめることを徹底しましょう。
夢絵禁止の基準は?
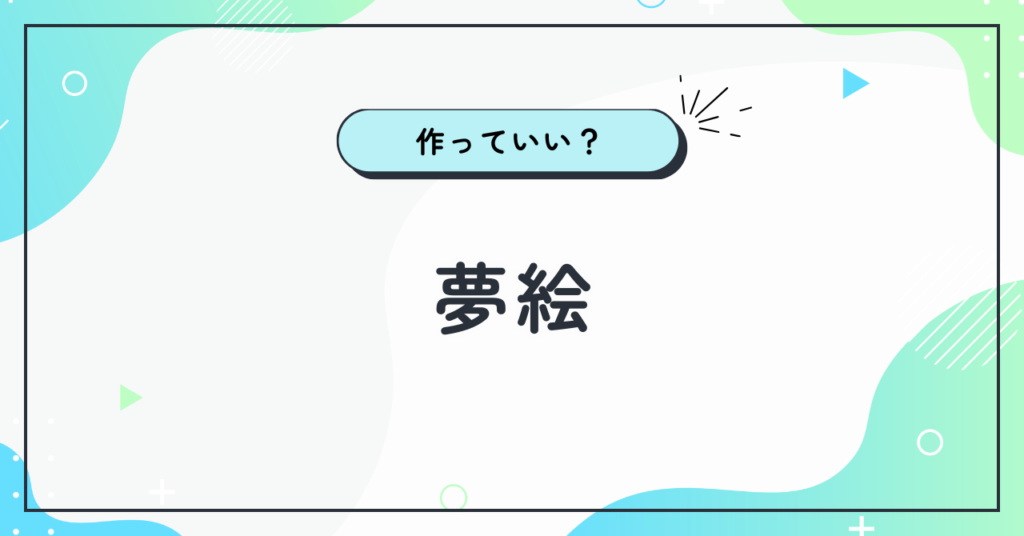
夢絵とは、ファン自身や他の人物をキャラクターとして描き、公式設定にはない関係性やシチュエーションを創作するイラストのことを指します。
自分の推しキャラクターとの恋愛シーンや性的表現を含む夢絵は特にリスクが高く、あんスタ公式のガイドラインでは明確に禁止されています。
しかし、どこからが夢絵にあたり、なぜ禁止されているのか分かりづらいと感じている人は少なくありません。
公式二次創作ガイドラインでは、キャラクターのイメージを損なう創作や、コンテンツ本来の設定から逸脱した表現は原則として認められていません。
夢絵は、キャラクターを自分やオリキャラと恋愛的に結び付けることで「公式が意図していない人間関係」を作り出すため、このガイドラインに抵触する可能性が高いとされています。
とくに「キャラクターと自分の名前を入れて並べる」「カップルのような雰囲気を描く」といった行為は明確に夢絵とみなされるため注意が必要です。
しかし、「キャラクター単体のファンアート」や「キャラクター同士の交流を描いた二次創作イラスト」は、非営利かつガイドラインの範囲内であれば認められています。
つまり、夢絵が禁止される基準は「ファン自身やオリキャラが公式キャラクターの世界に介入しているかどうか」にあります。
また、SNS上では「名前を入れただけでも夢絵になるのか?」という疑問も多く見られます。
結論として、キャラクターがファン自身やオリキャラと恋愛的・親密な関係を持つ表現は夢絵扱いになりやすく、公式から指摘されるリスクが高いです。
実際、過去には夢絵をSNSに投稿したことで批判や炎上に発展したケースも報告されています。
まとめると、夢絵が禁止される基準は「公式キャラクターとファン個人(またはオリキャラ)を直接的に絡ませる表現」が含まれているかどうかにあります。
あんスタのグッズ販売のルールは?同人イベントで気をつける点
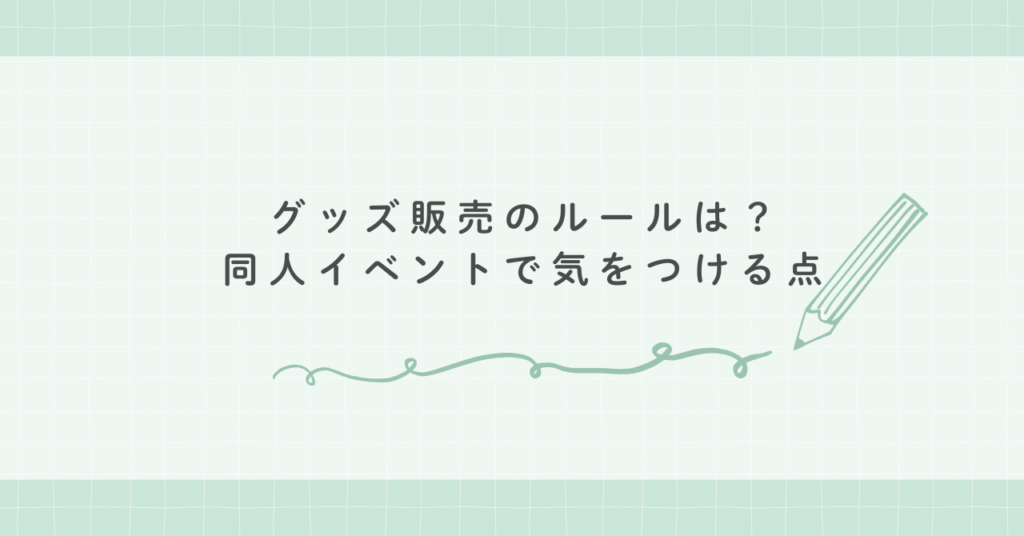
結論から言うと、あんスタの公式が定める二次創作ガイドラインにおいて、グッズ販売は非常に制限が厳しく、同人イベントでの頒布も細心の注意が必要です。
あんスタの同人グッズ販売で気をつけるべき点は以下の通りです。
- 公式画像・スチル・ロゴを無断使用しない
- 公式グッズと紛らわしいデザインを避ける
- 営利目的と見なされる価格設定や大量生産をしない
- ネップリや公衆送信による配布は避ける
- SNSやイベント告知でも公式素材を使わない
同人イベントで許容されるのは、あくまで自分で描いたオリジナルの二次創作イラストやデザインを使ったグッズです。
しかし、この場合でも注意点があります。
例えば「公式ロゴの使用」「公式グッズに酷似したデザイン」「誤解を招くパッケージや告知」は禁止対象となります。
これらは商標権侵害や混同を招くおそれがあるため、ファン活動の範囲を逸脱する行為とみなされます。
また、頒布形態にも制限があります。
ガイドラインでは、営利目的の販売は原則として認められていません。
同人イベントにおける「原価程度の頒布」は容認されることがありますが、過剰な価格設定や大量生産は営利行為と見なされるリスクがあります。
そして、事前予約販売や通信販売(BOOTHやメルカリなど)についても、条件次第ではガイドライン違反になるため、慎重な判断が求められます。
さらに、同人イベントでの展示や告知にも配慮が必要です。
公式イラストの無断転載や、あたかも公式と関係があるかのような宣伝文句は避けなければなりません。
SNSで頒布情報を告知する際も、公式画像やスチルを使わず、自作のサンプル画像やイメージ写真を利用することが望ましいでしょう。
あんスタ二次創作で実際にあった炎上事例
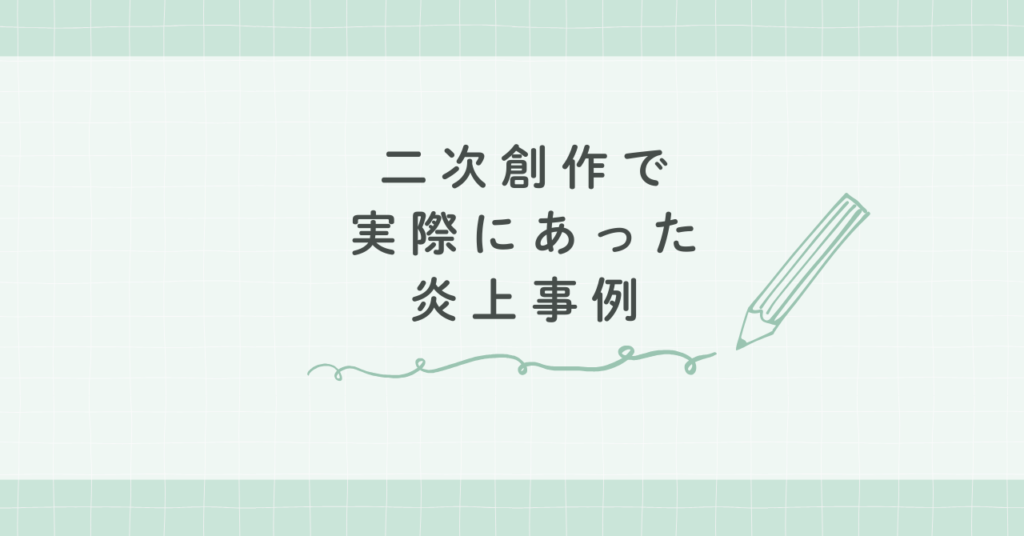
二次創作はファンにとって創作の楽しみですが、公式ルールを守らなければ思わぬトラブルに発展することがあります。
あんスタにおいても、過去にルールを逸脱した行為が原因で炎上や法的措置に発展したケースがあります。
ここでは過去の事例を紹介するとともに、、ルール違反がどのような結果を招くのかを紹介します。
事例①:キャラクター画像悪質加工事件
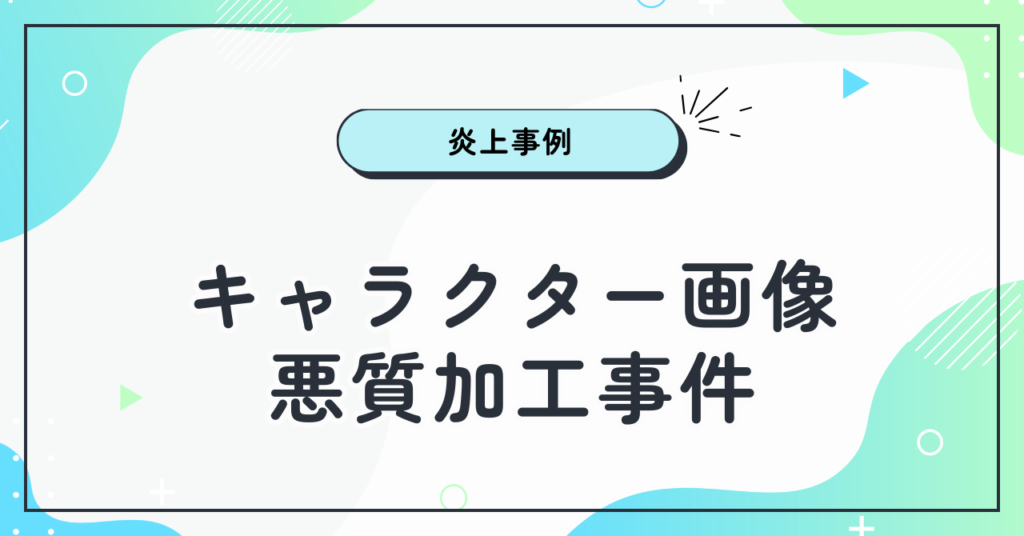
この事件は2024年6月に発生しました。
当時25歳の女性がゲーム内キャラクターの公式画像に虫の画像を貼り付けるという不快感を与える加工を施した上でSNS上に投稿しました。
その投稿は拡散され、多くのユーザーに衝撃と嫌悪感を与えた結果、京都府警により著作権法違反の疑いで女性は書類送検されました。
本人は取り調べで「推しキャラクターの扱いに不満があった」と供述し、容疑を認めています。
この行為が問題視された最大の理由は、「公式が提供するイラストをそのまま利用し、改変したうえで公開した」という点にあります。
著作権法では、私的利用の範囲を超えた無断複製や改変は明確に禁止されています。
特に不特定多数の人々が閲覧できるSNSへの投稿は「私的利用」にあたらず、権利侵害とみなされる可能性が高いのです。
今回のケースもその一例として捉えられ、警察による書類送検という厳しい対応に至りました。
なお、この件については後に不起訴処分となったことも報じられていますが、それでも「悪質な画像加工は法的リスクに直結する」という事実が強く印象付けられました。
本件の背景として押さえておくべき点は、運営会社であるHappy Elementsが以前からこうした行為に対して警告を発していたということです。
2023年4月には、不快感や恐怖心を与える加工画像をSNS上で公式アカウントに送り付ける行為が問題となり、同社は法的措置を取る方針を公表しました。
運営は「ファン活動の範囲を逸脱し、他者に不快感や恐怖心を与える行為は許容しない」という明確な姿勢を示したのです。
実際、2023年11月30日には東京地方裁判所にて、悪質ユーザーを相手取った損害賠償請求訴訟を提起しています。
その訴訟内容には「著作権侵害」「著作者人格権侵害」「営業妨害」といった項目が含まれており、発信者情報の開示請求が裁判所に認められたことを受けての対応でした。
つまり、今回の事件は突発的な一件ではなく、公式が継続的に警告してきた「悪質加工問題」の延長線上にあるといえるのです。
この事件は、二次創作やファン活動を行う上での大きな警鐘となりました。
特に、SNS上での拡散力は非常に強く、一度投稿すれば削除してもスクリーンショットや転載によって半永久的に残ります。
そのため、感情的になって衝動的に不適切な画像を作成・投稿することは、自分自身を法的リスクに晒す行為となりかねません。
また、この事件から読み取れる教訓は、「推しキャラの扱いに不満がある」などの個人的感情を理由に、公式素材を改変して攻撃的な表現に使うことは絶対に避けるべきだということです。
あんスタの運営は、こうした行為を単なるマナー違反ではなく、著作権や著作者人格権の侵害、さらに営業妨害として厳格に対処しています。
結果として、この事件はファンコミュニティ全体に強い影響を与え、二次創作活動のガイドラインや法的リスクについて改めて見直す動きが広まりました。
あんスタファンに限らず、他ジャンルのファン活動においても「創作の自由」と「法律・規約の遵守」のバランスがいかに重要かを示す象徴的な事例と言えるでしょう。
事例②:Arte Refact楽曲提供事件

この事件は2021年に発生しました。
Arte Refactは、あんさんぶるスターズ!! の数多くの楽曲制作を手掛けてきた有名なクリエイター集団であり、ファンからも信頼と注目を集める存在でした。
しかし、そのArte Refactが、別のVTuberグループへの楽曲提供を行った際に、あんスタの世界観を強く連想させる表現を使用してしまったことが問題となりました。
具体的には、提供楽曲の歌詞の中に「あんスタ」を直接的に示すわけではないものの、特定のキャラクターやストーリーを思わせる単語やフレーズが含まれており、ファンからは「これはどう見てもあんスタを意識している」「公式作品に携わる立場を利用した私物化だ」との声が上がりました。
さらに問題を深刻化させたのは、楽曲ジャケットのデザインでした。
そのデザインが、あんスタの既存楽曲ジャケットと非常によく似ており、構図や配色の点で「模倣ではないか」と疑問視される事態に発展したのです。
こうした要素が重なった結果、SNS上では瞬く間に批判が拡散。
「公式クリエイターである以上、あんスタの世界観を守るべき立場なのに、他のコンテンツに流用するのは裏切り行為だ」といった厳しい意見や、「あんスタのブランド価値を損ねる行為だ」という声が多く寄せられました。
ファンの間で大きな炎上に発展したことで、Arte Refact側は事態を重く受け止め、公式に謝罪文を公開しました。
しかし、この謝罪文の内容もまた賛否を呼ぶこととなります。
声明では「意図的にあんスタを想起させる意図はなかった」としつつも、類似性や誤解を招いた点については謝罪するという、どこか曖昧な表現が用いられていました。
その結果、ファンの一部は「誠意が感じられない」「言い逃れにしか見えない」とさらに反発し、炎上の火に油を注ぐ形となってしまったのです。
この事件が象徴するのは、公式クリエイターや運営に近い立場の人間が関わる表現活動において、ファンが非常に敏感であるという点です。
ファンにとって「あんスタの世界観」は特別なものであり、そこに他作品の要素が混じり込むことを強く嫌います。
特に公式関係者が他のプロジェクトで類似の表現を行うと、「あんスタを利用しているのではないか」と受け止められやすく、その反応は一般的な二次創作やファン活動以上に厳しくなります。
最終的にArte Refactは謝罪をもって事態を収束させようとしましたが、この一件で「公式に関わる人間が世界観を逸脱することのリスク」が浮き彫りになりました。
そしてファンの間では「あんスタの公式クリエイターでさえ批判されるのだから、私たち二次創作者もガイドラインをきちんと守らなければならない」という意識が広がるきっかけともなったのです。
あんスタはネップリは禁止?二次創作における著作権とガイドラインから見る注意点を徹底解説! まとめ
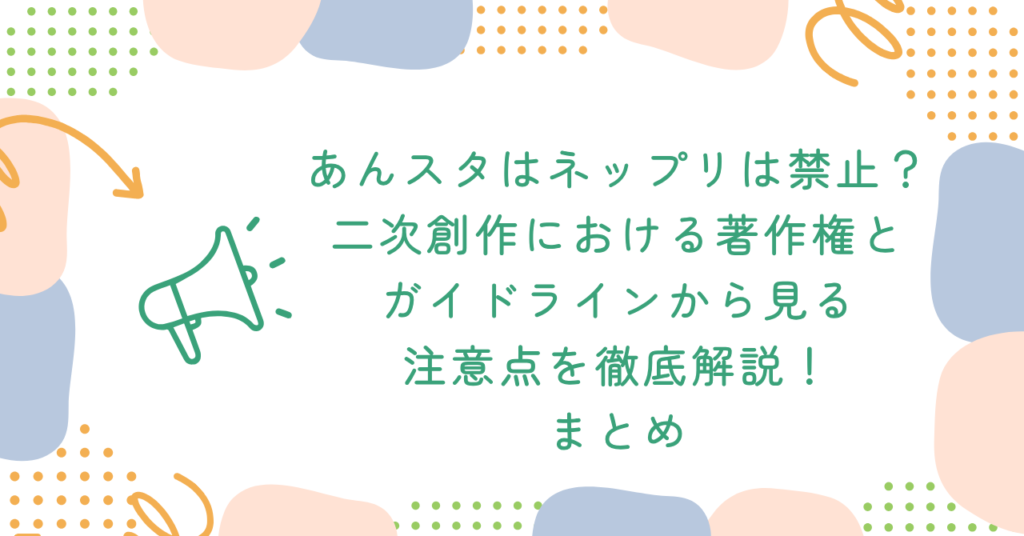
記事の内容をまとめます。
当ページは、Happy Elements株式会社「あんさんぶるスターズ!!」の画像を利用しております。 該当画像の転載・配布等は禁止しております。 ©Happy Elements K.K